
今回は人気Webライター、マダムユキさんに『オフィス環境から読み解く、地方中小企業の未来と危機感』をテーマに特別寄稿して頂いたコラムの掲載です。
世は、大倒産時代。
私が住んでいる地方のニュースでは、すでに「この地域では、企業の倒産件数が過去最大になりました」というニュースが毎月のように流れている。
これからの5〜10年で、地方の中小企業はバタバタ倒れていくだろう。それは「かもしれない」というぼんやりした予想ではなくて、必ず起こると決まっている容赦ない未来なのだ。
これから来る激動の10年を生き残っていける地方の会社は、残念ながらわずかしかない。
そもそも地方の中小企業には、事業を承継する後継者が居ないことが多い。世襲がモットーである親族経営の会社で、社長がすでに70代というところは珍しくないが、彼らの子や孫に会社を受け継ぐ意思がないのだ。
なぜ親の会社を継がないのかといえば、シンプルに将来性がないからである。
社長と一緒に設備と社員が老いていった会社を継ぐとなると、大規模な設備投資と若い人材が必要になる。けれど、多額の投資をしたところで回収できる見込みはないし、若い社員を雇いたくても、わざわざ地方の中小企業に就職したい若者は居ない。地方の小さな会社にとって、大卒の新卒採用など夢のまた夢になってしまった。
だったら大きな賭けに出るよりも、痛みの少ないうちに会社を倒産なり解散させた方がマシなのだろう。
後継者に誰も名乗りを上げないような魅力ない企業が、これまで辛くも生き残ってこられたのは、超低金利と人余りが続いたおかげである。
これまでは金利負担が軽かったからこそ、体力のない企業でも借入れを増やせたし、人余りだったからこそ、超がつく低賃金で労働者を雇い、いくらでもこき使うことができたのだ。
けれど、そんな時代も今や昔。
金利のある世界が復活した上、地方では少子化と若者の流出による人手不足がすさまじいスピードで進んでいる。あまりにも若者が居なさすぎて、近頃では私のような中高年でも就職や転職が簡単になってきた。
ここへきて、経営者と労働者の力関係が逆転したのだ。
今や会社が人を選べる時代ではなくなり、労働者側がいくらでも職場を選べる時代になっている。
けれど、労働者が強くなった弊害も無視できない。
ベテラン社員たちの立場が強くなりすぎてしまったことで、仕事の手順も環境も、もはや経営者の一存では変えられなくなったのである。
地方の中小企業は、人手が足りない中でどうにか現場を回しているところがほとんどだ。新しく人を採用できる見込みがなければ、今いる社員に辞められると非常に困る。
そして、地方の中小企業で「現場を回している社員たち」は、ほとんどが40代〜60代という「大きな変化を嫌う」年齢になっている。
いくら中高年でも転職しやすくなったとはいえ、40歳を過ぎると、大抵の人間は変化を嫌い始める。馴染んだ環境が変化することも、その変化に対応することも、大きなストレスになるからだ。
新しい環境に飛び込んで、慣れない仕事の手順を一から覚え、新しい上司や同僚との関係を構築し直すしんどさに比べたら、たとえ給料や待遇に不満はあっても、慣れた環境に居続ける方が心地よい。
そんな風に、転職もせず、業務や環境が変わることも嫌がる社員が束になって、変化への抵抗勢力となっていく。
すると、経営者は時代と社会の変化に気づいていても、社内を変えようとはしなくなる。
改革しようとしても社員に反発されるのがオチだし、そもそも自分にしたって若くないので、面倒なことはしたくないのが本音だから。
「これまで通り」の仕事のやり方で、「今のまま」の状態をまだしばらく続けられるのであれば、今すぐ変わらなくたっていい。
いつかは変わらなければならないとしても、今すぐじゃなくてもいいだろう。どうしても必要な時が来たら、少しずつやればいいじゃないか。
なんて考えの甘い経営者の下では何が起こるかというと、数少ない若手社員が退職していくのである。
ただでさえ日本はDXが遅れている上に、AIもほとんど活用されていない。
田舎の中小企業では尚更だ。いまだに会計ソフトすら導入されておらず、経理は古参のオバチャン社員が、電卓を叩いて計算していたりする。
「うちは流石にそこまで古くないですよ〜」と余裕をかましている会社でも、サポートが切れかけの古いバージョンのExcelに、いちいちデータを手打ちしている有様なのだ。
「えっ? それって、今の時代に人間がやる意味あるの?」
という非効率な作業に忙殺される職場に、今どきの若者が居着くはずないだろう。
平成どころか昭和が続いているような職場の状況に、若者たちは、初めに驚き、次に呆れ、やがてすっかり諦めて、都会へと逃げ出していく。
そして若者が消えた地方の中小企業は、ますます組織が硬直化して、変化への適応能力を失っていくことになる。こうなってしまうと、後は死(倒産)を待つばかりだ。
この5年の間に、都会と地方、大企業と中小企業との差は、恐ろしいほど開いてしまった。
コロナ禍をきっかけに、都会の大企業が従業員の働く環境を見直して、インフレと人手不足に対応して賃上げする一方で、田舎の中小企業はまだ「コロナ前の世界」に戻ろうと足掻いている。
人手不足を言い募り、従業員の勤労意欲の低下を嘆き、「これ以上の賃上げには耐えられない! 国は俺たちを潰す気なのか?!」と悲鳴を上げる中小企業の経営者たち。
自分たちが従業員に生産性の低い働き方をさせていることは棚に上げて、民間企業のくせに「国の支援が必要だ」と甘え続けている。
これまでは、そうやってごねていれば、どうにかしてもらえてきたのだろう。
けれど、もはやそんなフェーズも過ぎようとしている。
我が国には、いよいよ金がない。
それでも中小企業には、今は盛んに補助金がバラ撒かれている。
DXのための補助金、社員をリスキリングするための補助金、オフィス移転のための補助金・オフィスにIT機器やソフトを導入するための補助金、生産性向上のための補助金、etc。
けれど、こうした支援がこの先も続くと思わない方がいい。
国と自治体がせっせと補助金をばら撒いているのは、いよいよ始まる中小企業淘汰の時代を前に、言い訳づくりをしているだけなのだから。
「自分たちはできる限りの支援をしました。それでも変わろうとしなかったのは、皆さんご自身の問題ですよね」
と言うために。
甘んじて死を受け入れるなら、引導が渡されるまであと数年、今のままを続ければ良い。けれど、もし生き抜こうとするのであれば、手始めにオフィスの大改造から始めることだ。
地方でも気の利いた会社では、フリーアドレスを取り入れて、オフィスのレイアウトを抜本的に見直している。そうすることで、社員にも働き方を強制的に変えさせているのだ。
昭和でも平成でもない、令和を感じるオフィスには、若い社員たちが揃っている。
激動の時代に未来があるかどうかは分からなくても、ちゃんと「今」を生きていると感じられる職場でなら、若者たちも働きたいと思うのだろう。
一方で、「タイムスリップしたのかな?」と思うような昔ながらの事務所で働く人たちは、誰もが内心で「この会社は長くない」と分かっている。業績の良し悪しは関係ない。
たとえ現時点では黒字を出していても、未来どころか現代の空気すらない会社に若い働き手は寄りつかないので、10年以内に人手不足で倒産することが確実である。
変わるチャンスは、今しかない。
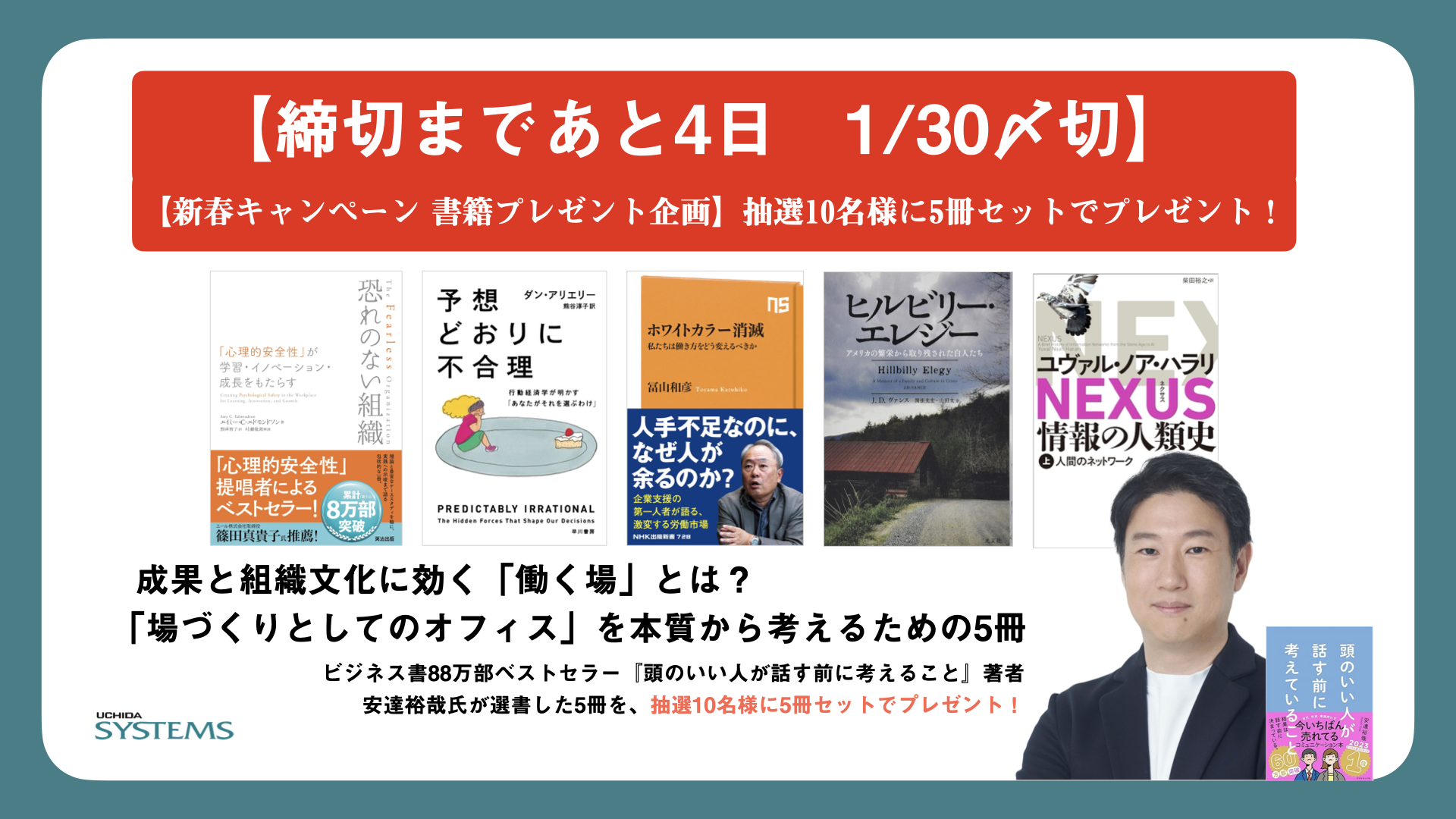
この記事を書いた人

マダムユキ
note作家 & ライター
https://note.com/flat9_yuki
※本稿は筆者の主観的判断及び現場観察に基づく主張であり、すべての読者に対して普遍的な真実を保証するものではありません。
組織力の強化や組織文化が根付くオフィス作りをお考えなら、ウチダシステムズにご相談ください。
企画コンサルティングから設計、構築、運用までトータルな製品・サービス・システムをご提供しています。お客様の課題に寄り添った提案が得意です。
